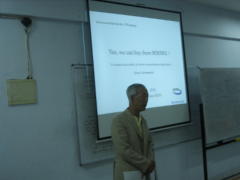|
●インドネシアロンボク島地震被害 (2018-8-10)
報道されておりますように、セリウェ(SERIWE)海藻プロジェクトの現場であるインドネシアロンボク島で、7月29日マグニチュード(M)6.4、8月5日M6.9、8月9日M6.2の地震が連続して発生しております。このため本プロジェクトは、現地住民の通常生活への正常化が優先されているため、しばらく活動は休止とならざるを得ません。進展があり次第HPで紹介いたします。
●セリウェ海藻加工PJ その後 (2018年7月3、4、6日)
三井物産環境基金終了後約半年経過しましたが、その後の状況、課題のフォロー、今後の展開方法について尾園代表理事、保坂理事、南山会田中代表等が、SERIWEサイト、マタラム大学、DPU等関係者と協議してきました。若い海藻(品質、生育の早い)での新たな藻場の展開、市場開拓、商品改良等継続して支援を進めて行きます。7月6日には、DPUのプロジェクト関係者、大学院生等とのフォーラムを開催し知恵を出し合いました。また近くでのリゾート開発も厄介な問題です。
|

|

|
|
outer bayの新たな藻場の計画
|
良好な新種の海藻の成長
|
|

|

|
|
ダルマプレサダ大学でのフォーラム
|
近隣のリゾート開発から自然を守る
|
●三井物産環境基金の支援が終了しワークショップを開催 (2017年9月21日)
9月13日、ロンボク島セロン町の東チーモール州中小企業庁にて、庁関係者、海洋漁業局、プロジェクト関係者(ダルマプルサダ大学、地元マタラム大学、セリウェ村組合長並びに関係者)等約50名以上が参加し盛大にワークショップが開催された。ダルマプルサダ大学Kamaruddin教授のプロジェクトの紹介、セリウェ村漁業組合長Syafuddin氏工場運営状況課題、マタラム大学からの海藻加工品に対する製品改良、品質向上などの今後の取り組みが説明された。これに対し企業局、漁業局等が課題を認識・共有し、協力していくことを約した。これからが本当のスタートであり関係者の支援をお願いしたい。
|

|

|
|
中小企業局
|
kamaruddin教授
|
|

|

|
|
Syafuddin漁業組合長
|
会場の様子
|
●浄水器で製造された飲料水の地元民への提供 (2017年6月20日)
ロンボク島セリウェ漁村の海藻加工工場では採れた海藻を乾燥させる台を、網から竹敷板に変更し生産性・品質を向上させるようにしました。また工場で太陽光・風力を電源とした浄水器で製造される飲料水が地元民に提供出来るようになりました。工場は着々と地域に根差したものとなってきました。
|

|

|

|
|
リニューアルされた海藻乾燥台
|
フル稼働の浄水器
|
飲料水の地元民への提供
|
●ワンタンチップ出荷開始 (2017年1月10日)
セリウェ湾で獲れた海藻からのワンタンチップの商用生産がいよいよ始まりました。まだまだ出荷量は少ないですが、セリウェ村の近くのJerowaru村のミニマーケットでの認可が得られ販売が開始されました。これを弾みに販売網を広げていきます。
●ロンボク島セリウェ村海藻加工工場の状況 (2016年12月24日)
・SERIWE漁村生活の一コマ
生活の糧をきれいな海から得ているのに海岸はゴミの散乱が目立ちます。今後海岸クリーンアップ作戦を展開する
予定です。タコを1kg300〜600Rp(3〜6円)で仲買人が買取りに来ており一日一人100円の生活ではあるがそこに
働くSERIWE村主婦の表情は明るいです。
|

|

|

|
|
海水のきれいなセリウェ湾
|
浜にはゴミが散乱・・・
|
朝取りタコの集荷風景
|
・SERIWE湾での海藻の養殖の状況
ペットボトルを浮子に利用125mx125mがー人分の養殖範囲となっています。収穫された海藻は成長した部分を取り、若い部分はまた海へ戻して養殖を行っています。
※海藻は年々老化して来ているので、ロンボク島Mataram大学が新たに開発した養殖手法で、藻場の若返りを今回のPJと連携して進めています。
|

|

|

|
|
ペットボトルを浮子として利用
|
養殖中の海藻
|
海藻の摘み取り
|
・SERIWE海藻加工工場
4月の製造経験を踏まえ、マタラム大学と共同して味、食味、包装袋等の改善を実施し新たな商品もラインアッ
プに加えました。またSERIWE主婦を中心とした作業員のトレーニング第二次をおこない、現在20人規模の作業員 体制となっています。今後地元SERIWE、マタラム市などロンボム島での販売、DPU生協での販売等拡販活動を進めていきます。
|

|

|

|
|
手慣れた手つきでの製造風景
|
ラインアップされたチップ類
|
ショウケースに陳列された商品
|
・海藻加工工場の移管
製造設備が完成し作業員の教育も終了したので、設備・製造・管理を地元協同組合(Cottoni Cooperative)へ 移管しました。
|

|

|
|
設備・製造・管理の移管調印式
|
プロジェクトメンバーの記念撮影
|
|
中央:DPUカマルディン教授
|
ダルマプルサダ大学・マタラム大学・
協同組合・REPA・南山会
|
|
左:Cottoni協同組合長
|
三井物産ジャカルタ支店
|
●ロンボク島海藻加工工場での試作開始とセミナー (2016年4月23日)
インドネシアLOMBOK島SERIWEプロジェクトは順調に進んでおり、海藻加工工場での試作が開始されました。
試作しているのはSERIWE湾で獲れる海藻を、太陽熱で乾燥し、太陽光パネル・風車で発電した電気で海水淡 水化装置を運転し、得られた清浄水を用い海藻ゼリー、海藻チップスを製造しています。このように再生可能エネ
ルギーを多用した食品製造工場となっています。
海藻の加工、製品化に当たっては、LOMBOK島MATARAM大学AQUACULTURE STUDY PROGRAMの協力を 得て進めています。今後は食品衛生体制を確立し、インドネシア厚生省等の認可を得て本格生産体制に入る予
定です。
今回はソリフィン学長が報道陣を引き連れてSERIWEを訪問しマスコミにPRするとか、できた商品をまずは大学生 協で販売するなど、大学が全面的に支援しています。
|

|

|
|
現地関係者への取材状況
|
浄水装置の前でおいしい水を
|
現地訪問に先立ち4月16日にはセミナーが開催されました。午前中は学部3,4年生が参加しソリヒン大学長の挨拶に続き、カマルディン教授より、ダルマプルサダ大学の紹介、研究室の活動内容、日本工業大学のものづくり
環境学科雨宮隆教授より、日本工業大学の紹介、大学での太陽光利用、雨宮研究室の活動内容を紹介し、 質疑応答などが活発に行われました。セミナー後は記念植樹を行いました。今後共このような交流を継続して行く
予定です。
|

|

|
|
DPU学長ソリヒン氏挨拶
|
カマルディン教授講演
|
|

|

|
|
日本工業大学 雨宮教授講演
|
セミナー風景
|
午後からは大学院生を対象としてとして、カマルディン教授よりSERIWEプロジェクトの進捗状況を、REPA代表理事 尾園次郎氏より食品衛生の重要性と管理方法を、最後に南山会前代表田中俊太郎氏よりインドネシアと日本
の多くのプロジェクトを増やしていくために、それぞれ講演し質疑応答、意見交換なされました。
|
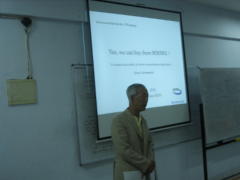
|

|
|
REPA尾園次郎代表理事講演
|
南山会 田中俊太郎前会長講演
|
●ロンボク島海藻加工工場地元へ引き渡し (2015年12月25日)
海藻乾燥工場、海藻加工工場の建物が完成し、12月12日セリウエェ村地元のCOTTONI協同組合への引き渡
し式が、COTTONI協同組合、ダルマプルサダ大学、セリウエェ村、東ロンボク州などの関係者が参列し盛大に行われ
ました。
1月からは、COTTONIの作業員への太陽光発電装置、風力発電装置、浄水装置の取扱い・運転・保守などの教
育が行われます。そしていよいよ海藻加工設備が導入され試作が開始される予定です。
|

|

|
|
三井物産、ダルマプルサダ゙大学、
マタラム大学、コットニィ協同組合、
東ロンボクセリウェ村
|
海藻乾燥・加工工場引き渡し式
|
|

|

|
|
引き渡し書類調印
|
中央がDPUのkamaruddin氏
右側が協同組合責任者Syaifuddin氏
|
工場周辺にもフェンス、敷石が敷設され環境、衛生面の配慮もされております。
|

|

|

|
|
正面浄水タンク、左側フェンス
|
昔砂地であったところに
ブリックで敷詰め
|
右が海藻乾燥工場
|
●ロンボク島現地進行状況 (2015年10月31日)
海藻乾燥工場、海藻加工工場の建物が完成し、9月からいよいよ海藻乾燥作業が始まりました。従来は海岸で の天日乾燥ですが、天候・風等などの影響により、乾燥レベル、乾燥時間、砂等の異物混入など、いろいろな問題があり安定した品質を得ることが大変でした。これからは乾燥工場内で安定した連続した作業となり、異物除去も
容易になります。品質も安定するので良素材を提供する事が出来ます。
|

|

|
|
これまでの天日乾燥
|
工場内での連続した安定した乾燥
|
また、乾燥工場、加工工場建屋周辺の環境整備も始まり、海砂・廃棄物などの海藻素材・加工製品への異物
混入防止が図られ、領域美化がなされ、お客さまが安心して海藻を買い求めることが出来ます。
|

|

|

|
|
以前建屋周りは砂地で、石・ごみなどが散乱していました
|
敷石を敷き詰め環境美化改善を行いました
|
海藻乾燥工場内床もプレー
トを敷き詰めました
|
●ロンボク島現地進行状況 (2015年8月31日)
現地では加工工場、海藻乾燥建屋が完成し、製作中であった、海水淡水化装置、風力発電機、太陽光パネルが次々完成し、LOMBOK島SERIWE村現地での据付試運転調整が進められております。井戸水タンク、クリーンウオータタンクならびにポンプ・付帯配管も終わり残工事が残されているのみの状況です。海水淡水化システムの試運転では村人達がきれいな水を飲めるようになり喜んでおります。これまでは隣村から飲料水を買っていたのが、
これからは逆に売るようになるかもしれません。再生可能エネルギー活用のよい事例です。
|

|

|
|
加工工場屋上に設置された太陽光パネル
|
加工工場屋上に設置された風力発電機
|
|

|

|
|
淡水化装置の前で美味しいお水を飲んでいるプロジェクトメンバーとセリウェ村民の方々
|
|
We can live even
without electricity, but we cannot live without clean water. Oh, yes! Life
is not sustainable without clean water while we may manage to live even
without electricity.
|
●ロンボク島現地視察と打ち合わせ (2015年4月17日〜26日)
4月17日から27日に掛けて尾園副代表が現地視察・打合せのため出張しました。ロンボク島セリウェ村では海藻 工場の建物と、太陽光−風力乾燥ヤードがほぼ完成しました。これから太陽光パネル、風力発電装置、海水淡
水化装置・井戸水タンク・クリーンウォータータンクなどの補機設備などが設置される予定です。
|

|

|

|
|
海藻加工工場外観
|
海藻乾燥ヤード
|
歓迎昼食会(海の幸が一杯)
|
●雑誌「財界」での活動開始紹介 (2015年1月13日)
本活動が開始されたことが雑誌「財界」2015年1月27日号(1月13日発売)P81に紹介されています。
表題は−戦後70年・改めて問われる日本の対外交流のあり方−
日本の経済外交の将来図を示すインドネシアとの「草の根」交流です。
●ロンボク島現地調査と打ち合わせ (2014年11月18日〜25日)
本プロジェクトの責任部門であるインドネシアのダルマプルサダ大学(DPU)のシーハン学長、カマルディン大学院長 (前学長)と、プロジェクトの最終ゴール、日本側の支援方法について話し合い、難問、課題はいろいろ出てくると
思うが協力して解決して行こうと決意を新たにしました。
その後セリウェサイトを調査し現地の方々と打合せをし、建屋・井戸の位置、海藻加工工場レイアウトなど協議しました。またロンボク島のマラタム国立大学を訪問し付加価値のある海藻加工の協同研究、ロンボク州政府を訪問
し本プロジェクトの協力・支援をお願いし、いずれも成功裡に終えることが出来ました。
|

|

|

|
|
左からカマルディン大学院長、尾園
REPA副代表、田中南山会代表、シーハン学長、学長室にて。後ろの額は元福田赳夫首相の訪問時の揮毫
|
セリウェ村での打合せ後の集合写真。現地では盛大な歓迎を受けた。ここは近海魚・海藻の採取で生計を立てている
|
ロンボク州政府(Government of West Nusa
Tenggara )トップ(中央)との打合せ。本プロジェクトの理解と協力支援を戴いた
|
|